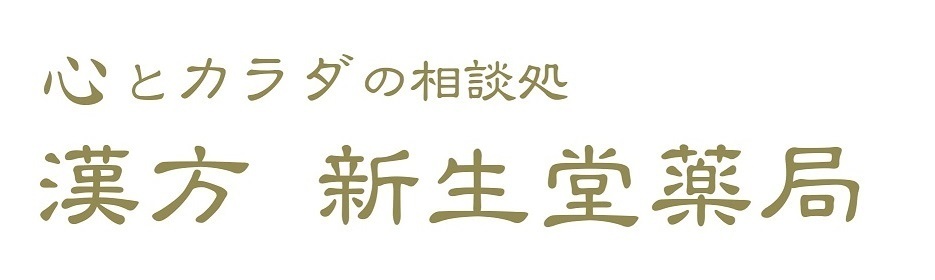埼玉県越谷市の漢方新生堂薬局です。不妊症・更年期障害・めまい・耳鳴り・腰痛・神経痛・アトピーなどでお悩みの方はご相談ください。
よくある質問
漢方薬は長く飲まないと効かない?
そんなことはありません。
「漢方は体質改善の薬なので、長く飲まないと効かない」といったイメージをお持ちの方は多いでしょう。しかし、これはよくある誤解の一つです。
例えば、軽いカゼならば、1回の服用で効果があります。また、長く咳止めを飲んでも治らなかった方が、漢方薬であっという間に治ることもあります。もちろん、適切な漢方薬を服用することが条件です。
一方、慢性化した症状については、一定の時間が必要です。しかし、例えば西洋治療を続けても治らなかった「めまい」や「神経痛」が、漢方で短期間のうちに治せることも少なくありません。
どのくらいで効果があらわれるかは、病気の種類や程度、その人によっても変わります。漢方の専門家であれば、服用する前に一定の目安を教えてくれるはずです。
漢方薬は副作用がなくて安全ですか?
正しく選び、正しく服用すれば安全です。
本来の性質を熟知した医師や薬剤師から処方された漢方薬であれば、副作用の心配はほとんどありません。
漢方薬は、一定のルールと経験をもとに生薬を組み合わせています。年齢や体重、症状や体質を考慮し、正しく選び、適切な量を服用すれば、無理なく自然にカラダのバランスを調えることができます。
逆に、こうした性質を熟知しないまま、安易にお薬を選べば副作用のリスクが高まります。
例えば、病院から2~3種類の漢方薬を処方されているケースがあります。複数の漢方薬を同時に服用するとなると、同じ生薬を必要量以上に服用することになります。当然ながら、副作用のリスクが高まるわけです。
一方、お年寄りや体力が低下した方など、身体の状態によっては慎重に服用しなければならない場合もあります。
過去に、漢方薬の小柴胡湯(しょうさいことう)による重大な副作用の事案がありました。医師から処方された小柴胡湯を服用し、それによって「間質性肺炎」を起こした患者さんが亡くなられたのです。その数は、当時の厚生省の報告によれば少なくとも41人にものぼります。
原因は、「慢性肝炎患者」に安易に長期にわたって処方し続けたことにあります。生薬の働きや、副作用について全く知らないままに、ただマニュアルに沿って病名だけで漢方薬を選んだことが原因です。
漢方に熟知した専門家であれば、このように小柴胡湯を使うことはなかったはずです。
以後、小柴胡湯については慎重に使われるようになりました。ただ、これは小柴胡湯に限ったことではありません。それにもかかわらず、いまだに安易に処方されているケースが散見されます。
- かぜのひき始めに葛根湯(かっこんとう)
- 内臓脂肪が気になる方に防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)
- 尿漏れ、頻尿に八味地黄丸(はちみじおうがん)
こうした分かりやすいキャッチコピーは危険です。
ご自身の判断で服用せず、漢方の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
他のお薬との飲み合わせは大丈夫ですか?
必ず漢方の専門家にご相談ください。
漢方薬は天然の生薬で作られているという安心感からか、飲み合わせを心配される方は少ないようです。
しかし、漢方薬であっても、飲み合わせによっては危険なものもあります。
過去に、問題となったのは病院で処方されるインターフェロン(慢性肝炎の薬)と漢方薬の小柴胡湯の飲み合わせによる間質性肺炎という副作用です。肺胞と肺胞の間に炎症が起こる病気です。
また、意外に知られていないのが、複数の漢方薬が処方される場合です。
漢方を正しく認識していれば、いくつもの漢方薬を同時に処方することはまずありません。本来の漢方は、症状と体質から「証」を考えてお薬を決めるためです。
残念ながら、漢方に精通した薬剤師や医師はそう多くはいません。「病名」や「症状」だけで安易に漢方薬を選んだり、複数の漢方薬を処方してしまっているのが実状です。
これでは、本来の効果が得られないばかりか、副作用のリスクも高まります。
例えば、多くの漢方薬に含まれる「甘草(かんぞう)」という生薬。
複数の漢方薬を服用することで甘草が重複してしまい、「偽アルドステロン症」という副作用のリスクが高まります。症状としては手足のだるさ、しびれ、むくみ、こわばりや筋肉痛などです。ひどいと麻痺(まひ)や動悸なども生じます。
大切なのは、ご自身で判断せず、必ず漢方の専門家に診てもらうことです。(→漢方薬局の選び方)
漢方なら何でも治せる?
漢方は万能ではありませんが、希望はあります。

『傷寒論(しょうかんろん)』
困ったときの神頼み、困ったときの漢方・・・、悩める気持ちはお察しいたします。現に、私も漢方にたずさわる以前はそう思っておりました。
しかし、漢方は決して摩訶不思議な「神秘」などではありません。
しばしば、「西洋医学は科学」「漢方は非科学」と言われます。
果たしてそうでしょうか?
西洋医学は科学と言われますが、過去に常識とされていたことが、現在では訂正されることが少なくありません。「科学」には理論的な根拠も必要ですが、それを裏付ける十分な経験も必要ということです。
最新の理論は、果たして十分な経験を積んだと言えるでしょうか?
漢方の歴史は数千年前にまでさかのぼります。まだ西洋医学が生まれていない時代です。当時は、自然界のあらゆる草根木皮や鉱物を毒味する、いわば人体実験を繰り返して薬効を一つずつ認識していました。
そうして、有効な組み合わせを ”レシピ” として完成させたのが漢方薬です。これらを『傷寒論(しょうかんろん)』という書物にまとめたのが2,000年も前のことです。以降、これを漢方のバイブルとして、膨大な経験を積み上げながら、理論のアップデートを繰り返して病気の治療に取り組んできました。
いわば、汗と涙の結晶・・・それが漢方というわけです。
漢方は、ときに西洋医学でも解決不可能な病気を治します。しかし、これは「神秘」などではなく、独自の理論によるためです。馴染みにくいだけに、納得のいくまで分かりやすくご説明することが必要と考えております。
大いに期待して、私どもに委ねてください。
希望をもって治療に取り組んで頂きたいと思います。
同じ名前の漢方薬ならば同じ効果?
必ずしもそうとは限りません。
漢方薬は様々なメーカーが製造しています。
エキス剤でも、ツムラ、クラシエ、コタローなどがあります。病院でよく処方される保険適用の漢方薬はツムラやクラシエが多いようですね。
さて、漢方薬の名前が同じならばどのメーカーでも同じかと思いきや、実はその中身はずいぶんと違います。
例えば、エキス剤(粉薬)であれば、
- 原料生薬の生産地と品質
- 抽出方法(原料を煎じる時間と温度)
- 加工法(顆粒、細粒、錠剤、原末)
- 顆粒や錠剤に成形する賦形剤(ふけいざい)
- 有効成分量(エキス換算)の違い
などなど。
様々なメーカーを比べると、その「におい」からも生薬の質や鮮度が分かります。
当然ながら効果にも影響してきますので、漢方を専門としているお店であれば、良質な生薬にこだわり、取り扱いメーカーも吟味しているはずです。(→品質へのこだわり)
薬局によって価格が違うのはなぜ?
価格は、漢方薬の品質・治療技術を反映したものとお考えください。
今やどこでも漢方は手に入れることはできます。しかし、最適な漢方薬による最善の治療を施すには技術が必要です。
漢方専門薬局の価格は、「お薬代」というよりも「治療費」とご理解頂ければ幸いです。
例えば、美容室。。。
イメージ通りの髪型、髪質に合ったアドバイス、確かな技術力をもつお店では、その技術格差が価格に反映されています。
・・・・・・・・・
漢方の効果を左右するのは次の二つだと言えます。
- 正しい漢方薬を選定できているか
- 原料となる生薬の品質はどうか
まず、何よりも重要なのが最適な漢方薬の選定です。これは、どれだけ漢方に精通し、どれだけ経験を積んだかにかかっています。そして、何よりも治療センスが求められます。(→漢方薬局の選び方)
一方、漢方の原料生薬には等級があり、国産で野生栽培されたものや、品質管理の行き届いた生薬は香りや味わいもある良質なものです。漢方の専門性が高くなるほどに、生薬の品質にこだわるようになります。(→品質へのこだわり)
価格はこうしたことが反映されています。
病院と薬局の漢方はどう違うのですか?
薬局漢方は専門性が高いです。
病院でも漢方薬を処方されることが多くなりました。保険がきくため、長く服用しても経済的負担が少ないというメリットがあります。
ただ、長く服用するということは、漢方薬が効いていないということでもあります。漢方には即効性がないと言われますが、数ヶ月も実感がないということはありません。
実際、医師は現代医学のスペシャリストではあっても、東洋医学(漢方)のスペシャリストではありません(医師のうち漢方の専門資格を有しているのはわずが0.6%)。ちなみに、漢方のルーツである中国では、西洋医学と東洋医学とで大学が分かれているほどに、二足のわらじをはくことは困難なのです。
漢方薬を効かせるために、大切なことが二つあります。
- 適正な漢方薬を選ぶこと
- 質の高い生薬を用いること
適正で質の高い漢方薬を選ぶためには、高い専門性が求められます。それだけに、薬のプロでもある薬剤師の役割は大きいと言えるでしょう。