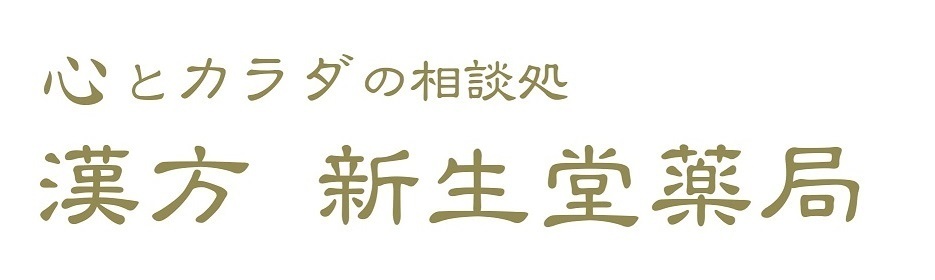埼玉県越谷市の漢方新生堂薬局です。不妊症・更年期障害・めまい・耳鳴り・腰痛・神経痛・アトピーなどでお悩みの方はご相談ください。
第43回 学生のための漢方講座
2025.08.17(日)
毎夏恒例の「学生のための漢方講座」(通称夏ゼミ)にて、漢方を学ぶ意欲のある学生さんたちに講義をして参りました。
今年の担当は「弁証論治」です。
実際の症例を提示し、参加者にはグループディスカッションにより弁証論治と漢方薬を考えていただきました。
・・・・・
取り上げた症例は、「腹痛・泄瀉」と「腰痛・右下肢のしびれと痛み」の二つです。
まずは、患者さんから得た情報を、表裏・寒熱・虚実・陰陽とう八綱で弁証します。
ここで大切なのは、弁証は不確定要素の積み上げに過ぎないという認識です。一つの要素だけで決めてしまうのではなく、多方面の情報から検討することが大事です。
腹痛・泄瀉について言えば、まずは痛みの性質から弁証の手立てを探ります。あるいは、便の性状も手掛かりとします。ただし、これらはあくまでも患者さんの主観による情報であり、相談員の解釈と合致するとは限りません。つまり、不確定要素に過ぎないということです。
腰痛の症例についても、同様のことが言えます。加えて、脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニア・腰椎すべり症・頸椎症・変形性腰椎症など、画像診断を根拠とした病名は、弁証の手掛かりとはなり得ません。なぜならば、腰痛の8割以上は骨の変形とは無関係な非特異的腰痛であるからです。裏を返せば、痛みの原因の多くは筋肉の変質にあると言えます。
漢方では、「どんな原因で」「どこで」「何が」「どうなった」を考えて弁証論治していくものです。単に、症状や病名だけで漢方薬を決めることはできないのです。
・・・・・・・・・
参加者の多くは、この二日間で得た学びを活かし、正しい弁証論治を導き出していました。この経験を踏まえ、学校や日々の生活に活かしていただけたら嬉しいですね。
ぜひ、来年の夏ゼミの参加をお待ちしております!
漢方相談の実際
2025.06.22(日)
今回は、皆様からご要望の多かった排尿トラブルの弁証論治について、実際の相談事例をもとにお話しました。
・・・・・
大前提として...
「頻尿には〇〇」といった秘策はありません!
大切なのは、「どの漢方薬を使うか」ではなく、「病態をどのように考えるか」です。それは、つまり弁証論治をすることです。
排尿トラブルのなかでも相談事例の多い排尿痛・頻尿・切迫性頻尿・夜間尿の4つの主訴について、弁証論治の決め手となるポイントについてご紹介いたしました。
排尿痛・頻尿については、八綱弁証における「寒熱」「虚実」を重視します。切迫性頻尿・夜間尿については、膀胱の硬化・萎縮といった膀胱の変質に着目し、「陰陽」も併せて考えます。
この膀胱の変質は、年齢的な要素が大きく、可逆性のもの不可逆性のものとに分けられます。同様の症状であっても、病態は全く異なるため、使う方剤も変わってくるわけです。
また、膀胱炎についても触れました。
膀胱炎は、「尿道からの上行性経路による細菌感染によって生ずる膀胱粘膜の炎症」というのが定説となっています。この細菌とは、多くの場合は常在菌である大腸菌です。ただ、常在菌であるにもかかわらず「細菌感染」という言い方には違和感があります。「細菌増殖」ならば分かるのですが…。
細菌感染となると、抗生物質でしか治らないということになってしまいます。ところが、実際には抗生物質では再発を繰り返し、漢方を頼みの綱としてご相談に来られる方が少なくありません。
このことからも、膀胱炎の原因は「細菌感染」ではなく、 ”結果” でしかないことが分かります。真の原因は、何らかの要因によって膀胱が炎症を起こし、その結果として「細菌増殖」したに過ぎないものと考えます。そのため、抗生物質によって一時的に細菌が減ったとしても、膀胱の炎症が除かれなければ完治しないのです。
膀胱炎に漢方が有効なのは、この膀胱の炎症を鎮めることができるためです。その結果として細菌が減っていくのです。
では、膀胱の炎症とは、何がきっかけとなるのか?
私見ですが、疲労と冷えによるものと考えております。そこで生じるのが、多くは陰虚内熱によるものです。これが現代にいう炎症ということです。陰虚内熱では、膀胱の炎症以外にもは口唇の乾燥・手足のほてり・尿が黄色くなるなど、患者さんから確認すべきポイントがあります。
このように、漢方の強みは、原因療法にも寄与できるところです。
今回の講義では、それぞれ症例をあげながら具体的にご紹介させていただきました。
講義の中でも触れましたが、大切なことは次の通りです。
・病名漢方ではなく弁証論治をすること
・症状や年齢に応じて標治と本治に優先順位をつけること
毎回申し上げていますが、「△△(症状)には、〇〇湯(漢方薬)」といった秘策はありません。
思い込みは禁物です。患者さんから必要な情報を掘り起こし、発せられる情報を聞き漏らさず、随伴症状と混同せずに弁証論治をすることです。
この講義がそのための一助になれば幸いです。
前回、「弁証論治の探求(1)」では、弁証論治についての概論をお話しいたしました。
今回からは各論に入っていきます。
・・・・・
今年の冬はマイコプラズマから始まり、年末にかけてインフルエンザが猛威をふるいました。
インフルエンザの初期症状といえば、悪寒・頭痛・発熱・関節痛です。これは、漢方で言う感冒(傷寒)の初期症状と同じです。
漢方が考えられた古代中国では、インフルエンザもコロナもわかりませんから、冬季に同様の症状からはじまるものを「傷寒」と分類したのです。傷寒を分類し、治法を記したのが『傷寒論』という本です。
今回は『傷寒論』をもとに「感冒」の漢方治療についてお話しします。
「感冒」で一番大切なのは、その症状がどの段階にあるのかと、症状の変化に応じた対応です。
感冒の段階には、「初期」「中期」「後期」の三段階があります。
この中で、最も大切なのは「初期」段階での対応です。この段階では、悪寒・頭項強痛・脈浮といった表証が中心です。そこで、迅速に、正しく漢方治療ができれば、その後の症状の長期化・重症化を防ぐことが可能です。
「中期」に入ってしまうと、発熱が著しくなり、関節痛や筋肉痛、あるいは咳・鼻汁が始まります。すると、どのような治療法であっても、ある程度の時間を要することになります。漢方においても、使える薬が限られてきます。
そこで、この時期は対処療法的にはなりますが、ある程度症状を和らげてあげることで予後の悪化を防ぐことができます。
「後期」に入ると更に治療が難しくなってきます。実は、漢方薬局にご相談にいらっしゃるのは、この段階の方がほとんどででしょう。
微熱が続いたり、空咳が長く続いていたり、倦怠感や息切れ、胃腸の不具合などの訴えが多くなります。病院でも手立てがなく、漢方に救いを求めにいらっしゃるのです。
状態によっては、完治するまでに時間がかかる場合もあります。そこで、患者さんには、あらかじめ治療期間の目安をお伝えしてご理解いただく必要があります。
治療は難しくとも、漢方のお役に立てる時期と言えるでしょう。
今回の講演でお伝えしたポイントは、
・感冒の流れを知る
・今、どこの段階にいるのかを把握する
・邪気の強さと、生体の陰陽に則した漢方の選択
でした。
すぐに役立つ知識というものは、すぐに役立たなくなるものです。
”明日すぐには使えない漢方の話” だったかもしれませんが、日々の相談の中で経験として積み重ねることで、必ずや患者さんのお役に立てるものと思います。